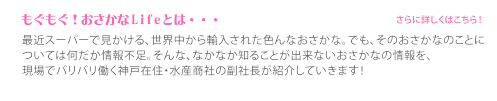私どもフューチャーフィッシュはニュージーランドから
キンメダイも輸入し、卸売しております。
日本近海での漁獲はかなり減少しているのは
もちろん・・・
世界の海でも漁獲減少には歯止めがかからない状況です。

これがニュージーランド産キンメダイ
私たちフューチャーフィッシュが輸入するのは、頭をとった状態で
冷凍保存し、輸入しております。
日本近海のものに比べると、ややオレンジがかっています。
供給が少なく、需要が多ければ、価格が高騰するもの・・・
このキンメダイにおいても、昨年の夏から価格は青天井になり
相場がグングンと上がっています。
相場後記
私たちフューチャーフィッシュは「水産商社」という位置づけの企業です。
そしてワタクシ副社長、何年も前からこのキンメダイの相場を追っかけ
卸売しております。
勝った(黒字)こともあれば、負けた(赤字)こともあります。
「商社」と「ブローカー」の違いは・・・と最近、考えることがあるのですが
大きく3つあるのかな、と。
1.商社は、自社で輸入している商品を在庫している
2.海外現地との直接取引なので、自社あての原産地証明がある
そして最近、ココを一番重要に考えるのですが
3.「商社」は出来る限り相場を安定させ、物流下である水産加工企業
問屋、量販店、飲食店のすべてにおいて、利益をもたらすように
価格設定に努力すること。
単発の「ブローカー」は、その一瞬、自分だけ儲かれば終わり・・という
考えの方も少なくはないと思います。
それによって、相場が乱れ、価格が高騰し、赤字経営を余儀なくされる
企業から悲鳴が聞こえてきます。
儲けが無くなった企業は、キンメダイをメニューからはずし
ますます魚のアイテムが少なくなっていきます。
この難しい時代、単発で儲けを出すような「美味しい話」などは皆無に
等しいと思います。
ワタクシ副社長、微力ですが「水産商社」として、ココを踏ん張って
いきたいと思います。 おわり!
今日から、また寒波がやってきて日本海側は大雪とのこと。
ワタクシ副社長、島根へ行く予定をキャンセルしてしまいました。
神戸もシンシンと冷えてきております。
さて、当社フューチャーフィッシュは、子供をもつお母さんに「魚食」に関しての
意識調査を行いました。
子供さんを保育園に預けて、日中はお仕事をしておられる、神戸で最も多忙な
お母さん100名にアンケートを実施いたしました。
本日は、個人的に興味のある質問事項を2つ取り上げてみました。
1.フィッシュ&ロックバンド「漁港」という、ロックに合わせてマグロ解体ショーなどを
行うバンドがあります。ご興味はありますか?

こちらが、「漁港」のボーカル 森田釣竿船長です!(^^)!
回答:
・イベントがあれば、ぜひ子供を連れて行ってみたい! 48%
・興味がない 50%
・回答なし 2%
#「ぜひ、行ってみたい」と回答された方の中で、4名の方は「漁港」の
森田船長を知っている、もしくは名前だけは聞いたことがある・・・という
回答をいただきました。
2.ある日の夕方スーパーへ行き、「今夜のおかずは肉料理にしよう~」
と決めました。なぜですか?
回答:
1位 肉のほうが安い!!
2位 調理しやすい、 調理のレパートリーが多い
3位 片づけが簡単、または、ごみ出しの日、生ごみの
日程を見てから・・
4位 肉のほうがボリュームが出る
5位 魚料理と肉料理を交互にメニューに入れている
(その他、少数意見です)
・おさかなが嫌い
・余っても保存しやすい
・近くに新鮮な魚を売っている店がない
・自分で魚をさばけない・・・
・魚の調理は部屋に匂いがつくから
・子供の給食のメニューがその日は魚料理だったから
・翌日のお弁当のおかずにもできる
・下処理が必要ない
消費者である主婦の方々は、家族の命を支えている・・といっても
過言ではない、と思います。
そして、そのお気持ちはアンケート結果にも顕著に出てきている
ように思いました。
ワタクシ副社長の実家・島根では、おさかなの一夜干しや
フィレにしたもの、または切り身にして味付けがしてあるもの・・・など
旬の脂ののったおさかなを冷凍庫で保存する習慣があります。
今回の回答で気になったのは、お肉は冷凍するけれど、おさかなを
冷凍するという感覚がないのかな・・・と。
「魚食普及」について、まずはココから考えてみる、またはアナウンス
していく。
まだまだ、取組む手立てはあるように思います。
2月に入り、寒い日が続いております。
この寒さで脂がのっているのが「天然鴨」:-P
何年も前から、ど~しても行ってみたかった
小郡にある「さとう別荘」さんへ連れていっていただきました!
ここ「さとう別荘」さんは11月中旬から2月中旬までの期間限定
で、「天然鴨」のお刺身をいただける、全国でも唯一の場所。
特に今の時期は、脂もかなりのっておりトロ~リとしたお刺身
がいただける・・・とのこと。


ここ「さとう別荘」さんは大正時代の豪富がたてた別荘にて、お屋敷も
中庭も大正ロマンの香りがイイ感じ。
そして、コレが名物「狩場焼」

専門の焼き鍋
ねぎの方は、平になっており、鴨の方は傾斜がついていて
鴨の脂が自然に落ちる仕組みになっています。

そして、横浜冷凍さんのエライ方々とおかみさん:oops:

九州後記
ワタクシ副社長、「男の哲学」というか「男の仕事術」というか・・・
勉強中です。
起業して13年。
顧客を接待したことがなかった・・・です。軽~く市場食堂にてお昼ごはん
というのはありましたが。
水産業界という男性社会の中で、ヘンに夜のお付き合いをすることを
避けていた、ところがあります。
広いようで、狭いこの水産業界の中、「フューチャーフィッシュの副社長は
飲ませて仕事とってる」と後ろ指をさされるのではないか・・・
そんなウワサがたたないように、昼間のビジネス上でだけ登場するように
心がけておりました。
最近、社長についてまわってデビューしております。
「お金の使い方」、「気の使い方」などによって、仲間や部下がついてくる上司
と、そうでない方。
仲間に囲まれたボスは、傍から見ていてもカッコイイです
次、生まれ変わるとしたら男性で生まれたいかも・・・
いや、やっぱり女性はやめられません。
だって、やはりコレですよ。

中州の女には負けられんとよ~!(^^)!
明けましておめでとうございます。
本年も、よろしくお願いいたします。
昨年、年末まで仕事をしており、左脳ばかりを使っておりましたので
新年早々、お正月花を生けてみました。

この花器は、ワタクシ副社長、人生で初めて作陶したものです:roll:
同友会でご一緒の西海社長にお世話になって、昨年11月に
立杭の陶芸の先生のところで初体験しちゃいました!
縁起の良い、梅と松、そして南天・・・
南天は「難を転ずる」として、お正月のお花にはかかせません。
お花を生ける前は、この花器はこんな感じ。

結構、イケてない感じ・・・:-D
それでもって、土が少し残ったので、それを使って先生がパパッツと作ってくださった
作品

先生ですから・・・・
生花後記
お花だけでも、花器だけでも目を引かないものが
融合することで、華やかさを増し、魂を吹き込まれるような感覚
になる・・・
華道というのは、お互いのものを引き立たせることで、それぞれの
存在価値を出すことができるのかな・・・と。
日本の文化・芸術は、改めて素晴らしいと感じます。
ワタクシ副社長も「自分が・・・自分が・・・」の精神ではなく
他人と協調し、認め合って成長していければ。
そんな素晴らしい人格になるのは、いつの日か~☆ つづく!
今日は11/20 神戸マラソンが行われています。
7時~10時フラワーロードは封鎖され、車両は入れない
と通知があったのですが、ちょこっと打ちっぱなしに行って
やはり自宅に戻れず、事務所に来てしまっています((+_+))
この夏の思い出といえば、一番大きかったのが
浦安で開催された「RE FISH]に参加したことでした。
「RE FISH」とは・・・
日本人の良き食文化である魚食に戻ろう!!
をスローガンに水産に関係する様々なジャンルの方々
の集まりであり、活動です。
9/18浦安で開催されたBBQには全国から250名が集まり
交流を図り、悩みを打ち明けあい、親交を深めました。

この日は浦安市場のスーパースター泉銀・森田釣竿さんの
マグロ解体ショーが和太鼓の演奏とともに繰り広げられました!

森田釣竿さんは、FISH&ROCKバンド「漁港」のボーカル&リーダーを
努められ、全国ライブを行っています。
この日も和太鼓の音に合わせ、マグロヘッドの部位を
見事に取り分けていました。
もちろん、取り分けられた目玉の一つはワタクシ副社長が
いただきました~!(^^)!
このマグロヘッドは、すんごく鮮度がよかったので、変な臭みも
なく、BBQで焼いて、焼いて・・・香ばしかったです!!
イベント後記
この日は水産業界に関わる、仲卸、商社、流通、飲食、小売り
の様々は分野の人に出会うことができました。
そして、皆さんの思いは一つ「魚食普及・推進」
これに尽きます。
今後、このようなイベントを各地で開催していきたいのですが・・・
ワタクシ副社長の個人的な意見としては
業界同志で盛り上がるばかりではなく、この志をどのように消費者の
方々へ落とし込んでいくか・・・
これから日本の未来を背負ってたつ子供さんたちに魚を食べて
もらいたい。
イベントに子供さんたちの楽しそうな声が広がる・・・
そこから、ご両親、そして祖父母の方々へ
近海魚、輸入魚のこだわりなく、業界全般で消費者へうったえて
いく時期にはいったと思います。
わたしたちは情報を提供していく・・・そしてTPOに合うものを消費者が
選択していく・・・
このシンプルな形を取り戻すことから始めることができれば。
「魚食普及・推進」の糸口が見つけられるのでは、と思います。
- 初志貫徹!!!(17/02/27)
- キンメダイ フィレ(17/02/23)
- ヨガにはまってます(16/10/20)
- 10/2通関士試験受けまして~(16/10/17)
- 古民家のおそば屋さん(16/07/22)
- 2017年2月 (2)
- 2016年10月 (2)
- 2016年7月 (3)
- 2015年8月 (6)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年4月 (7)
- 2015年3月 (6)
- 2015年2月 (6)
- 2015年1月 (3)
- 2014年12月 (1)
- 2014年11月 (2)
- 2014年10月 (3)
- 2014年9月 (5)
- 2014年8月 (8)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (4)
- 2014年1月 (1)
- 2013年11月 (2)
- 2013年10月 (2)
- 2013年9月 (4)
- 2013年8月 (9)
- 2013年7月 (9)
- 2013年6月 (3)
- 2013年5月 (2)
- 2013年3月 (1)
- 2013年2月 (2)
- 2012年12月 (2)
- 2012年11月 (2)
- 2012年9月 (4)
- 2012年8月 (1)
- 2012年7月 (1)
- 2012年6月 (6)
- 2012年5月 (4)
- 2012年3月 (2)
- 2012年2月 (5)
- 2012年1月 (1)
- 2011年11月 (4)
- 2011年10月 (4)
- 2011年9月 (5)
- 2011年8月 (16)
- 2011年7月 (5)
-Keiko Tsumori-
1999年水産商社を起業。 ニュージーランド、バーレーン、パキスタンから年間約1000㌧冷凍水産物を輸入。出身の島根県の魚はもちろん、近海の旬の魚を食べるのが大好き。 夢は東南アジアで日本の生け花ビジネスを展開すること!!